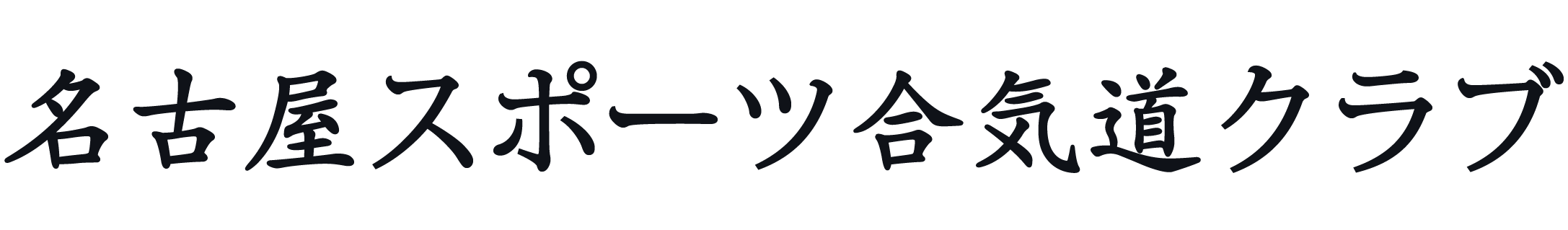形稽古との関係性
-形を守る-
乱取稽古は形稽古の延長線上にあります。まず形を学んで、次に乱取りを行い、そこで体験したことが形の理解を助けることになり、形の理解が進めば乱取技への応用範囲も広がります。形稽古は、「取」(攻撃する側)が固定されていたり、その順番が決まっていたりしますが、乱取稽古では文字通り「取」が「乱」れます。乱取りになった途端、その乱れへの焦りや合気道の技への自信の無さからか、普段の(合気道の)稽古で習うことのない動きや形からかけ離れた動きをしたりする人もいますが、それでは形を守ることができていません(その意味で合気道の技の学びが中途半端となっています)。
形稽古だけでは「かけきる」感覚を習得できません。相手が自由意志で動いていないのですから、本当にかかっているのかどうか、あるいは、本当に投げるための稽古ができているのだろうか、ということについて自分なりの確証を得ることが難しいです。結果として一つ一つの形の存在意義を理解できず、元々の形をいたずらに変化させてみたり試行錯誤したりすることで、時の経過とともに知らずしらず元の形から離れていきます。形は、万人が理合いを学べるように考案されたものであって、原則として、形稽古の中の形は崩すべきではありません。形の応用としての試行錯誤は乱取稽古の方で行うべきであり、スポーツ合気道ではそれが可能となります。
乱取稽古に求めるもの
-勝利に固執しない-
競技化においては、ルール作りによって、全力で技を出し合いながらも怪我のリスクを最大限抑えることが重要になります。全力を出しても怪我をしないからこそ継続的に稽古ができます。全力を出せることで「態度の真剣」が得られ、稽古が継続できるからこそ技術性の追求ができます(一方で「かたちの真剣」は薄れます)。いかに投げ抑えるか研鑽していく過程で筋力を向上させてみることも一つの良い経験になりますし、技の試行錯誤や取捨選択、試合中の咄嗟の判断を通じて精神力も培われ、心身を育む一助になると思います。
注意しなければならないのは、ただ相手を倒すだけなら無数の方法が考えられるところ、ルールの範囲内で技を行使し、勝ちを求めて勝利に固執せず、競技化の元となる武術の性質を見失わないように、乱取りで行う技は形稽古で学んだ技の延長線上にあるよう心がけることです。
乱取稽古の種類
乱取稽古の種類としては、短刀乱取と徒手乱取がありますが、短刀乱取では、最も重要な、間合を取ることの修練ができるため、短刀乱取から始めることを推奨しています(短刀乱取の主な留意点はこちら)。
さらにそれぞれの競技へも参加することで、実際どの程度思う通りに自分が動くことができるのかあるいは相手を動かせるのか否かについて、あくまでルールに則ったうえですが、その現実に触れることができます。始めのうちは、硬直したり形稽古での動きとかけ離れドタバタしたりと、全く思った通りに動けないし動かせないというのが普通ですが、乱取稽古や競技の繰り返しによって、自分に何が足りないのか肌で感じ、ようやく形稽古の意味を考えていくことができます。